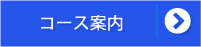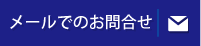VOICEインタビュー
<太陽有限責任監査法人>「データ・アナリティクス・スペシャリスト」の人材育成に本格的に取り組む!」(2/2)
太陽有限責任監査法人の監査業務推進部 部長、パートナー 公認会計士の柴谷哲朗先生に、ICAEA JAPANの代表理事弓塲が当協会のサービスを選択された理由や効果、ねらいを伺いました。

柴谷 哲朗先生 太陽有限責任監査法人 パートナー 公認会計士 監査業務推進部 部長 【略歴】 平成9年公認会計士登録。現在、太陽有限責任監査法人のパートナー。会計監査業務のIT化・業務改善に取り組んでいる。
—現在のCAATsツールの利用方法と対応、また今後の利用方法と対応について
弓塲:差し支えない範囲で結構ですので、現在導入されているCAATsツールの利用状況、今後の活用方針等についてお聞かせください。
柴谷先生:はい。現状では、サンプリングでの利用に留まっているというのが実情です。データ・アナリティクスへの利用は限られています。クライアントからデータを受領し、CAATsツールを使って、どのようにデータを処理して監査手続に結び付ければ良いのかなどのノウハウが法人内に十分に蓄積しておらず、CAATsツールを有効に活用するためには、まだまだやるべきことがあると考えています。
すでに、表計算ソフトを使った分析というのは、それなりに取り組んでおり、実務でも活用しているのですが、監査手続の再実施可能性の確保や監査調書の効率的な作成という観点からは、まだまだ改善の余地があり、解決すべき課題があると考えています。CAATsツールをもっと活用することで、これらの課題をかなり改善できるはずだと考えています。
弓塲:確かに、監査手続の再実施可能性の確保や監査調書の効率的な作成という意味においては、CAATsツールは、間違いなく表計算ソフトよりも、数段上のレベルで担保できると思います。現状、表計算ソフトで行っている領域の内、少なくともデータ処理部分をCAATsツールに置き換えることで、監査の効率性は間違いなく向上します。特に監査調書の作成については、CAATsツールの特長のひとつである『操作履歴がログに自動記録される』という機能を有効に使うと監査調書が自動的に作成できる方法があります。
柴谷先生:それは大変興味深いですね。今、私共がCAATsツールの有用性についてよく理解していない部分、監査調書の落とし込み方などを含めてノウハウを提供していただけることを、非常に期待しています。

弓塲:わかりました。そこは是非、研修でしっかりとお伝えしたいと思います。
—今後のICAEA JAPANに期待すること
弓塲:今後のICAEA JAPANに期待することをお聞かせください。
柴谷先生:はい。期待ばかりが膨らむのですが、最も期待するのは、貴協会が提案している仮説立案技能です。監査人のコンピテンシーとして、『良い問いかけができるか』ということと、『その問いかけに対して、実際に解決することができるか』という2つを考えた時に、後者については、取引記録のデータ化が現在のように進んでいなかった時代においては、取引記録の中からリスクの高い事象を抽出してその信頼性を監査証拠の入手によって確かめるといったプロセスに習熟していると思うのですが、取引記録のデータ化が高度になってくると、データがどのような形でテーブルに格納されているのか、どのように構成されているのかが分からないと、適切にリスクの高い事象を見つけることすらできなくなってしまうと思います。
データの中に自分たちが使える武器があることを理解した上で、データの生成プロセスやデータの持ち方、データの関係性などを理解するだけで、どのように課題を解決していくのか、自ずと答えが見えてくるはずです。データとデータを照らし合わせれば、不正シナリオに対する取引を抽出することもできるようになると思っていますので、そこに非常に期待をしています。これらは一連の思考プロセス、すなわち仮説立案技能に則って行われると考えますので、仮説立案技能こそが私たち監査人にとって身につけるべきスキルの一つだと思っています。

柴谷先生:一方で、データ処理や分析技能については、ツールの実行から調書化の方法までを含めた一連のフレームワークがあると思いますので、これらを取り入れることで業務の標準化・統一化が行われ、効率的な監査につながることに期待しています。また、データ分析の結果、興味深いデータ(結果)が得られ、これをビジュアル化することができれば、クライアントのマネジメントや監査役の方々にも非常に分かりやすく説明ができるのではないかと思っています。
データ自体が会話の糸口となって、私共からも、『良い問いかけ』を行うことができる。また、クライアントからも、私共に異なる視点でデータを見て欲しいというリクエストを受けるなど、ガバナンスに関して非常に有効な議論のきっかけになり得るとも思っています。こうした会社とのディスカッションを通じて、監査手続の深化を目に見えた形で感じていただくことで、クライアントから私共への新しい信頼に繋がってくるであろうと、そのように考えています。
弓塲:ありがとうございます。仮説立案についてはおっしゃる通りだと私共も考えています。私自身、CAATsに携わって20年以上が経ちますが、未だに「CAATsで何ができるのか?」という問いかけを少なからずいただきます。その問いかけの本質は、「CAATsで何ができるか?」ということではなく、「どういった手続が必要なのか?」といったことを問われているように感じています。つまり、監査手続の作り方について問われているのだろうと感じています。
こうした問題意識に基づき、監査手続の立案に必要な仮説立案というものを重視した研修プログラムを開発しています。仮説立案は、いわば目に見えないコンセプト(概念)を目に見えるように整理して文書化、言語化するプロセスといえます。研修では、このプロセスを監査に焦点を当てたフレームワークとして提示させていただき、反復練習で身につけていただきます。
また、データ処理・分析技能では、スクリプトというCAATsツールの簡易的なプログラムを作成いただくのですが、それも一目見て、どのような手続を実施しているのか分かるテンプレートを用意しており、スクリプトやテーブルのネーミングルールも定めています。これにより、どのような手続を実施しているのかが見易くなります。また、操作記録をCAATsツールではログといいますが、研修では調書用のログを作成する方法をご紹介し、監査調書の効率的な作成方法も練習していただきます。こうしたやり方を周知徹底していけば、他の担当者が実施した手続が一目で分かるようになるため、レビューも行いやすくなり、品質の向上にも繋がり、業務の引継ぎも容易になると考えています。これらの方法論を研修でお伝えしたいと考えています。
柴谷先生:はわかりました。よろしくお願いします。
弓塲:最後に、「データ・アナリティクス・スペシャリスト」の育成について、法人内においてどのような効果を期待されているかお聞かせください。
柴谷先生:そうですね、全国のマネージャーが集まって、10年後の法人についてディスカッションを行う機会があったのですが、その中で、私たちが行っている監査という仕事は将来どう変わっていくのか?仕事のフィールドが狭くなってしまうのではないか?という意見が少なからず出てきました。
データに関わることのできない監査人はこれから価値が薄れていってしまうかも知れない、そういうことに対するキャッチアップができていない危機感というのが、きっとあるのではないかと思います。従って、こうした教育の機会を持てるということは、非常に前向きに捉えてもらえるのではないかと考えています。
弓塲:やはり、そのように感じる方が多いのですね。私の持論ですが、監査人はAI(人工知能)やロボットに取って代わられるのではなくて、AI(人工知能)やロボットを使う職業になると思っています。
柴谷先生:なるほど。
弓塲:ただやはり、AI(人工知能)やロボットを使う監査人になるためには、データをきちんと扱える技能を身につけておかなければならないとも思っています。
柴谷先生:データ活用の世界が進んでくると、監査法人における人員構成の在り方も変わってくると思います。今から将来像をイメージして、どうせだったら一番先に皆がデータに強い監査法人になることを目指しませんか?と話をしています。
弓塲:それについて、皆さんどのような反応をされていますか?
柴谷先生:実際には、まだ実感されていないかもしれません(笑)。

弓塲:おそらく、今年の夏から研修をさせていただき、CAATsを実務に活用していただくことで、より身近なものとして感じていただけるのではないかと思います。
本日は、ありがとうございました。
太陽有限責任監査法人様は、明確な意図をもって、これからの監査人に必要とされるであろう「データを使って監査をする技法」を監査担当者全員が身につけるための取り組みに、本格的かつ本気で取り組まれていることが分かりました。その極めて重要な経営戦略の実現にICAEA JAPANが果たすべき役割が大きいことに身の引き締まる思いです。ご期待に沿えるように取り組んでいこうという決意を新たにしました。